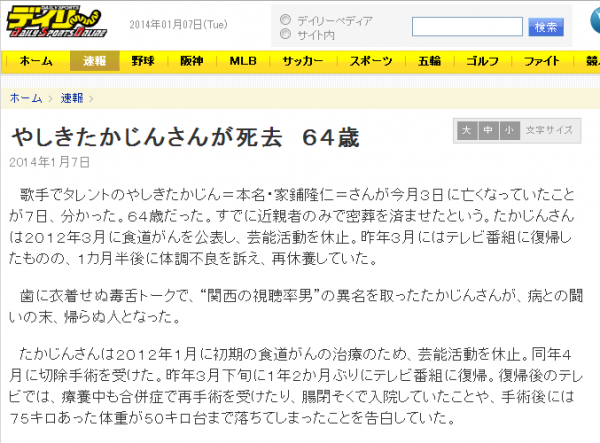![]() 朝ドラ『純と愛』において、ヒロイン(夏菜)が就職面接を受ける際に同じく応募者としてその場に出演していたのが女優の黒木華さんであり、その姿を見た瞬間に彼女に一目惚れしたという経歴を持つ当方が、映画『小さいおうち』(監督・山田洋次、主演・松たか子、助演・黒木華ほか)を見ましたよ。
朝ドラ『純と愛』において、ヒロイン(夏菜)が就職面接を受ける際に同じく応募者としてその場に出演していたのが女優の黒木華さんであり、その姿を見た瞬間に彼女に一目惚れしたという経歴を持つ当方が、映画『小さいおうち』(監督・山田洋次、主演・松たか子、助演・黒木華ほか)を見ましたよ。
近頃、玩具メーカーの重役・平井(片岡孝太郎)は東京の小高い丘の上に家を新築した。その家はそれほど大きなものではなかったが、西洋風のモダンな建築様式で真っ赤な瓦屋根を有している。近所でも評判の建物だった。平井には妻・時子(松たか子)と幼い息子の恭一(秋山聡)があった。
当時、ある程度の収入のある家では女中を雇うことが当たり前の事だった。新しく家を構えたこともあり、平井は新しい女中を雇うこととした。
そこへやって来たのが、山形の寒村出身のタキ(黒木華)だった。1年前に村を出る時こそしゃべりから訛りが抜けていなかったが、元々聡明であったことに加え、東京の小説家(橋爪功)の家で女中の基本を仕込まれたこともあり、平井家に来たとたんに立派に女中として働き始めた。
時子はタキのことをよくかわいがったし、息子の恭一も彼女によく懐いた。タキは一家のために全身全霊をかけて尽くそうと思うのだった。また時子は管弦楽や洋風の喫茶を趣味にするなど、先進的で洗練された女性だった。タキはそんな時子への憧れも強く抱くのだった。
ある年の正月、平井の玩具メーカーの新人デザイナー・板倉(吉岡秀隆)が年始の挨拶にやって来た。彼は美術学校出身で、就職した後もモダンな長髪で芸術家風だった。どこか社会の大人たちに馴染めない様子であるらしく、平井家の新年会でも会社の仲間たちと仕事や世情の話をするよりも、平井の子どもに絵本を読んでやる事の方が落ち着くらしかった。
時子とタキは、板倉の独特な雰囲気に惹かれた。
日本の戦局が悪化し、景気もひどく落ち込んだ。平井の務める玩具メーカーは材料不足や需要減少の煽りをもろに受けた。そんな中、会社の重役たちは独身の板倉に白羽の矢を立てた。彼を名士の娘と結婚させて、会社を支援してもらうことを目論んだのだ。多くの若者たちが戦地へ行っており、適齢期の男は少なかったのでチャンスがあったのだ。しかも、板倉は目と気管支が悪く徴兵される見込みがなかった。名士たちにとっても、娘婿が戦争へ行くことは望まないので願ったりかなったりだったのである。
数人の候補者がすぐに見つかり、板倉の見合いの段取りは時子に任されることとなった。夫に命じられてその役を引き受けたものの、時子は板倉が政略結婚の道具に使われることをよく思わなかった。板倉の方も自分に結婚はまだ早いと考えており、何かと言い訳をつけては見合いを断り続けた。話の進まないことを夫に叱責されながらも、時子は板倉の味方であり続けた。
見合いの打ち合わせとして何度も顔を合わせているうちに、時子と板倉は互いに強く惹かれ合うようになった。そして、板倉の下宿で男女の契を交わした。
ふたりの関係に最初に気付いたのはタキであった。見合いの打ち合わせに出かけた前後で時子の帯の結び方が変わっていたからである。しかも情交は一度きりではないらしい。加えて、御用聞きの酒屋(螢雪次朗)も彼らの関係を怪しんでいるらしく、彼はタキに気をつけるよう促すのだった。
タキは葛藤に陥った。時子を先進的な女性として崇めるタキは、彼女の恋愛を応援したいと思う。一方で、平井家の幸福や平和を第一に考えるタキは、時子の不倫を露見させるわけにはいかないのである。
日本の戦局はますます悪化し、徴兵の範囲が広がった。そのため板倉にも召集令状が届いた。
板倉が東京を発つ前日、時子は彼に会いに行こうとした。それをタキは押し留めるのだった。タキはふたりの関係が噂になりかけていることを忠告し、時子が出かけるべきではないと説得した。その代わり、彼を平井家に呼び出すのが良いと助言した。会社員が上司の家に出入りするのならば不自然はないからである。
タキは、時子に手紙を書くよう言い、それを自分が板倉に届けると申し出た。そうすれば彼はきっと会いに来るだろうと言うのだ。時子は短い文を封筒に入れた。それを預かったタキは、すぐに家を出て板倉の下宿へ向かった。
しかし、結局、板倉は会いに来なかった。
その後、日本の劣勢はますます激しくなり、タキは郷里の山形に帰ることになった。終戦後、タキは平井家の消息を訪ねに来た。そこでわかったことは、平井夫婦は庭の防空壕で抱きあうようにして死んでいたということであった。息子の恭一の行方は知れなかった。
平成になり、タキ(倍賞千恵子)は親戚・健史(妻夫木聡)の勧めもあり、平井家での思い出をノート数冊に書きあげた。彼女の死後、遺品整理中にタキが保管していた写真など、数点の平井家縁の品が見つかった。
ひょんなきっかけから、健史は平井家の息子・恭一や板倉の終戦後の足取りについて調べ始めるのだった。
続きを読む